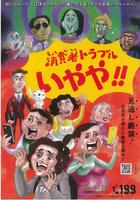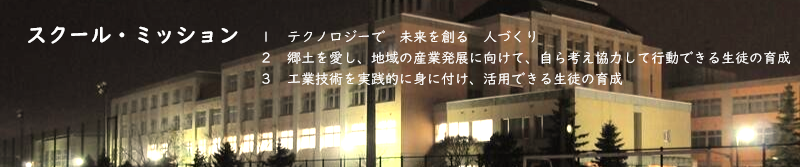
2025年7月の記事一覧
7月22日(火)全校集会
◎夏季体育大会表彰式、夏季休業前の全校集会
7月23日(火)、本校体育館にて、夏季体育大会表彰式と夏季休業前の全校集会が行われました。
夏季体育大会表彰式では、生徒会執行部から優勝した3学年に賞状が授与されました。
夏季休業前の全校集会では、校長先生からは、イランでの言葉を大切にする文化についての紹介から、言葉で人を喜ばせるのも傷けるのも自分次第であるという話をされました。教務部長からは、一部の生徒で欠席の多さについての心配があり、学校で学ぶことの大切さについて話されました。生徒指導部長からは、規則正しい生活をして、夏季休業中を自己成長の場にしてほしいと話されました。進路指導部長からは、就職・進学試験に向けてあるべき行動について、具体例を交えながら話されました。夏季休業を通して、心身ともに健やかに成長することを願っています。
7月18日(金)夏季体育大会
7月18日(金)、本校体育館にて夏季体育大会が行われました。今年度は各クラスでアンケートをとったところ、バスケットボールに決まりました。各学年の人数を調整して、6チームによる予選リーグ戦、勝者同士による決勝戦が行われました。結果は優勝3学年、準優勝2年電気科でした。白熱した試合、あふれる歓声、一致団結して臨む姿はまさにB1リーグそのものでした。この大会を開催するにあたり、生徒会執行部、バスケットボール部、有志の皆さん、準備と運営に協力してくれたありがとうございます。またこの大会を通じて、日常生活においてもポイントゲッターになるよう皆さんの努力に期待します。
7月17日(木)学校給食 その5
7月17日(木)、給食のメニューは五目ご飯、揚げ出し豆腐の野菜あんかけ添え野菜添え、味噌汁(玉ねぎ・卵)でした。生徒は洋食やラーメンなど高カロリーを好む傾向にありますが、定時制の給食では和食が出ることもあります。一汁三菜を基本とする日本の食事スタイルは理想的な栄養バランスと言われています。また、「うま味」を上手に使うことによって動物性油脂の少ない食生活を実現しており、日本人の長寿に役立っています。調理員の皆さん、ありがとうございました。
7月16日(水)美化活動
7月16日(水)1時間目に全学年で美化活動に取り組みました。琴似工業定時制では日頃より職業教育のあるべき姿を追求し、校舎内外をきれいにするとともに、地域の方々に感謝の意を込めて、美化意識の向上とその実践を行いました。生徒は蒸し暑い中、敷地内外と発寒地区の道路にあるごみを拾い、街をきれいにすることができて充実した活動になりました。
7月10日(木)遠足(ボウリング)・11日(金)芸術鑑賞
7月10日(木)、サンコーボウルにて遠足(ボウリング)が行われました。琴似工業高校定時制の最大のイベント、生徒はボウリングを思い思いに楽しみました。ボールを投げてガターになったときの悔しさ、ドヤ顔でのストライク、狙いを偶然定めてのスペア、仲間と共に絆を深めました。今後は、日常生活でのスペアからのストライクを決めてほしいです。
また、7月11日(金)、札幌フロンティアシネマにて芸術鑑賞が行われました。指定された内容からから自分で選んで、大スクリーンで臨場感あふれる映画を観ました。ワクワクと感動のストーリー、迫真の演技、一同驚愕のキャストたち、会場にいる観客と興奮を共有することができました。心に栄養をつける映画って本当にいいものですね。
7月9日(水)学校給食 その4
7月9日(水)、給食のメニューは、スタミナ丼、味噌汁(豆腐・油揚げ)でした。毎週水曜日、琴似工業定時制の給食は「〇〇丼」です。丼ものは、一杯のご飯に、肉・魚のたんぱく質、野菜のビタミンなどをまとめて摂れるので、気軽に栄養バランスを取ることができます。またアレンジ次第では、季節の野菜やお肉、魚介類などを使えば、無限にカスタマイズ可能です。まさに日中汗水流して働いて、夕方に勉学に励む琴似工業高校定時制の生徒にはぴったりの食事です。調理員の皆さん、ありがとうございました。
7月7日(月)ALT・イスラエル先生訪問 その2
7月7日(月)、ALT・イスラエル先生が1学年で授業をしました。最初にALTの先生がスライドを使って自己紹介をしました。最初のうちは緊張した様子でしたが、生徒は生の英語に触れることができました。次に生徒は自己紹介をしました。事前にワークシートに話す内容を記入して、オリジナルあふれる内容で、ALTの先生に伝えました。最後に数字を言うゲームをして楽しい時を過ごしました。今後は、恥ずかしがらずに積極的にコミュニケーションを図ることを願います。
7月2日(水) 1学年 消費者センター 契約に強くなろう!
札幌市消費者センター啓発員の方に、2年生家庭科で金融教育を始める前にあたって、断り方を身に付けたり、何かあったら相談するクセを身に付けていきます。
7月2日(水) 琴定WORK-WORK 職員研修
琴定WORK-WORK教員の学びでは、北星学園大学 文学部心理・応用コミュニケーション学科 片岡 徹 教授を招いて「貧困・ヤングケアラー支援」について中学校、高校教員時代の事例を交えて、子どもの貧困をSDGsや児童福祉法から教えていただきました。「生徒の背景を見取る必要がある。」という感想や「何故このような時代背景になったのか。今の高校教育でどこまで達成できるものなのかという問いが生まれ、もっと知りたくなった。」という先生がいて、とても深い学びにつながりました。