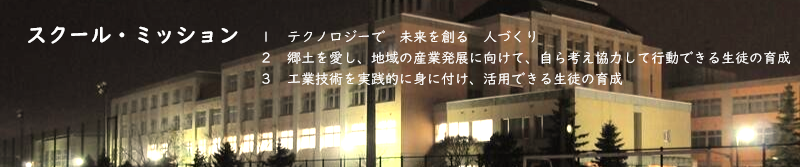
教育目標
・社会の変化に対応できる資質を養うため、基礎・基本を重視し、実践的な知識と技術を修得させる。
・電子機械技術の諸問題を主体的に解決する能力と態度を養い、心豊かで調和のある職業人を育てる。
電子機械科はメカトロニクスの基礎を学ぶところです。
メカトロニクスとは、メカニクス(機械技術)とエレクトロニクス(電子技術)から生まれた和製英語です。つまり、電子機械科では、従来の工業高校機械科で行ってきた授業や実習(工作機械による金属加工・板金溶接・金属部品の手仕上げ加工)はもちろんですが、電子技術であるロボットやNC工作機械(コンピュータ制御の工作機械)の制御やCAD(コンピュータによる機械製図)といった内容を学びます。もちろんコンピュータの基本操作からインターネットに代表されるコンピュータネットワークまで学ぶこともできます。
資格取得については、教室での授業や実習の中だけではなく、放課後の講習会などを通して資格取得に向けての個別指導も行っています。毎年多くの生徒が合格し、勤務している職場や就職活動に役立てています。
1年 工業技術基礎
工業技術の基礎となる分野について実習形式で学びます。効果的な授業とするため、クラス10人程度の班に分けて行う基礎的な実習です。
| 前期テーマ | 後期テーマ |
| 旋盤の基本操作と安全作業 | 旋盤加工の基礎 |
| 手仕上げによるマシンバイスの製作 | 文鎮製作、回路の基礎(テスター製作) |
| wordの練習 1 | wordの練習 2 |
| プログラミングの基礎(BASIC) | プログラミングの基礎(BASIC) |
電子機械科実習
2年から4学年まで、工業技術基礎より専門的な内容についての実習を行います。もの作りと情報技術をあわせた効果的な実習形態の授業です。
2年の実習テーマ
| 前期 テーマ | 後期 テーマ |
| 旋盤加工(丸棒・リングの製作) | 旋盤加工(豆ジャッキの製作) |
| ドローンの基礎 | ドローンの応用 |
| アーク溶接の基礎 | 溶接ロボットの基礎 |
| 工作技術(パズルの製作) | EXCEL実習(表計算Ⅱ) |
3年の実習テーマ
| 前期 テーマ | 後期 テーマ |
| NC旋盤の使用方法(1) | NC旋盤の使用方法(2) |
| wordとEXCELの操作 | リレー・シーケンス基礎応用 |
| 総合製作(組鉄) | 総合製作(工具箱) |
| 旋盤加工(ネジ棒・リングナットの製作) | 旋盤加工(トースカンの製作) |
4年の実習テーマ
| 前期のテーマ | 後期のテーマ |
| マシニングセンタの制御(基礎) | マシニングセンタの制御(応用) |
| ガス溶接の基本操作 | ガス溶接の応用作業 |
| 旋盤加工(地球こまの製作) | 旋盤加工(滑車の製作) |
| パワーポイントの基礎 | パワーポイントの応用 |
電子機械製図
2年から4年まで電子機械製図を学びます。 電子機械製図とは、従来の機械科の手書きによる製図の基本・基礎の授業から始まり、図面の書き方・読み取り方と進み、コンピュータによる製図(CAD)までを3年間かけて学ぶ授業です。 CADでは正確かつ綺麗な図面を作ることができるので生徒も集中して取り組んでいます。
課題研究
| テーマ |
|
作品製作Ⅰ(設計から製作までのものづくりの基礎を 学ぶ) |
| 作品製作Ⅱ(電子機械科の技術でギターなどの楽器製作を行う) |
| 作品製作Ⅲ(鍛造による製作) |
| 卒業記念DVDの製作を行う |
取得可能な資格
電子機械科では、資格取得に向けて、授業の中や放課後等にも学習会を実施しています。資格を取得することで、本校在学中に就職が決定したり、卒業後の進路決定に役立てる事ができます。
| 資格名称 | 資格の特徴 |
| 計算技術検定 | 1年の工業情報数理という科目の中で、関数電卓を用いた計算技術を学び、本校を会場に検定試験を実施しています。 |
| 情報技術検定 | 2年の情報技術基礎という科目の中で、取組試験に備えます。プログラム言語等に関する検定です。 |
| 危険物取扱者 | 学年問わず希望者が講習会に参加し、年2回の試験に臨みます。ガソリンスタンドだけでなく、危険物を取り扱う業種では貴重な資格です。 |
| ガス溶接技能講習 | 4年全員を対象に本校を会場として行われます。本講習を修了することにより、ガス溶接作業に従事することが可能となる資格です。 |
| 2級ボイラー技士試験 | 暖房や急騰に使用するボイラーの取り扱いが可能になる専門職の資格です。技能講習会や学科試験の受験講習を実施しています。 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
学校の連絡先
電話 011-661-3253
FAX 011-661-3252
Eメール sapporokotonikougyou-t0@hokkaido-c.ed.jp
住所 〒063-0833
札幌市西区発寒13条11丁目3番1号
学校についてご不明な点、ご質問等がございましたら上記までご連絡ください。
【通常時】平日13時30分から19時30分の間で対応いたします。



